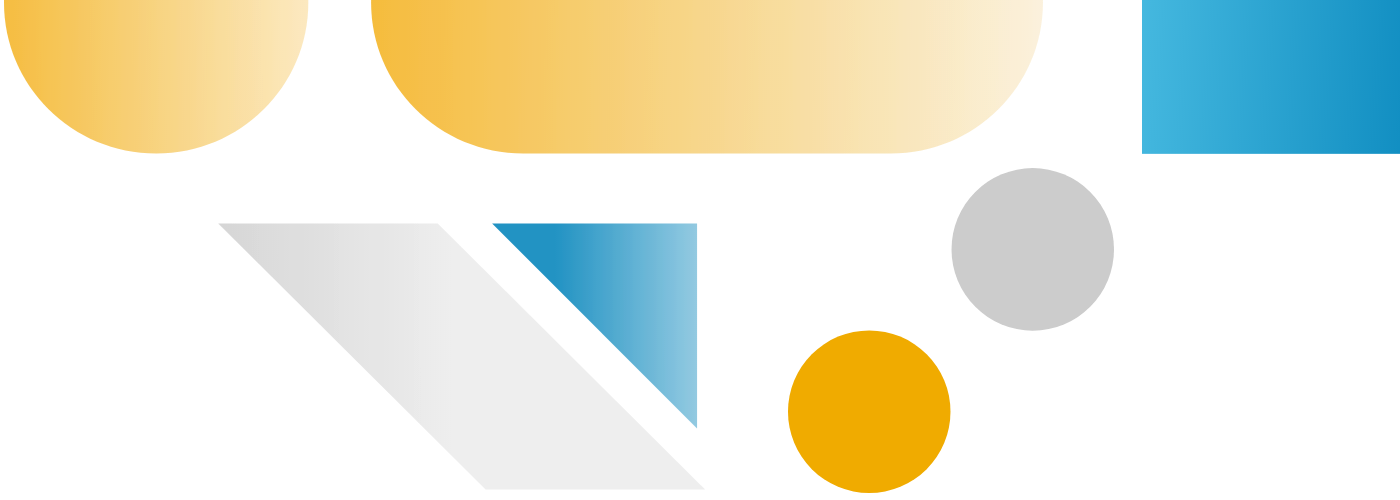連結原価管理とは?連結ベースでの収益向上に欠かせない管理手法(vol.122)
- 公開日:

製造業における原価管理は、企業の競争力を左右する重要な経営課題です。特に複数の子会社や関連会社を持つ企業グループでは、各社単独の原価だけではなく、グループ全体の原価を一体的に把握する「連結原価管理」の視点が不可欠です。
連結原価管理は、グループ全体のコスト構造を可視化し、経営判断の精度を高めるとともに、内部取引の最適化やコスト削減にも直結する強力な管理手法です。本記事では、「連結原価管理」の目的、実務上の課題、導入ステップ、システム実現手段について、わかりやすく解説します。
「連結原価管理」とは何か
まずは、「連結原価管理」とは何かを、以下のような製造体制をとっている企業グループを例に解説します。
-企業グループ–
- 子会社A社:原材料から部品を製造
- 子会社B社:A社から部品を仕入れ、半製品までを製造
- 親会社C社:B社から半製品を仕入れ、最終製品(X)を製造し、顧客へ販売
このような製造体制をとる企業グループでは、各社が個別に原価を管理しているだけでは、最終製品の原価や利益率を正確に把握することができません。例えば、親会社C社の原材料費には、子会社A社やB社の労務費や製造経費、粗利が含まれているため、企業グループ全体のコスト構造を正確に捉えることができません。また、製品Xの売価を検討する際に、個別の会社での原価計算のみでは、企業グループ全体での粗利や限界利益を把握できず、価格競争を強いられた場合に、グループ全体として利益を確保できる適切な売価の検討ができません。
そこで、以下の図の右側に示すように、企業グループ全体を一つの会社と見立てた「連結原価管理」の仕組みが必要となります。連結原価計算においては、企業グループをまたいで非累加※での原価積上げが求められます。また、企業グループ間の内部取引(部品や半製品のグループ会社間での売買)は、個別企業の利益分を控除したうえで原価計算を実施することが求められます。
※非累加=前工程の製造原価の構成要素(原材料費・労務費・製造経費等)を保持したまま次の工程に積み上げる計算方法

「連結原価管理」の目的とメリット
企業グループにおける原価管理は、単体企業の枠を超えた視点が求められます。「連結原価管理」は、グループ全体の原価構造を統合的に把握し、経営判断の精度を高めるための戦略的な管理手法です。ここでは、その目的と得られるメリットを、より具体的に解説します。
グループ全体の原価の可視化
複数の製造子会社や販売会社が関与する製品の原価は、個別企業の原価管理だけでは全体像が捉えられません。「連結原価管理」により、原材料から最終製品までのコスト構造を一気通貫で把握することが可能になります。
- グループ全体のコスト構造の一元的な把握
- 内部取引を含めた原価の流れの明確化
- 原価情報のグループ会社間での共有
経営判断の精度向上
連結原価情報を活用することで、製品別・顧客別・地域別の収益性を正確に分析できます。これにより、以下のような戦略的意思決定が可能になります。
- 利益率の低い製品の見直し
- 高収益製品への資源集中
- 適正な販売価格の設定
内部取引の最適化
グループ内の取引価格(移転価格)が適正でない場合、利益の偏りや税務リスクが生じます。「連結原価管理」では、内部取引のコスト構造を明確にし、合理的な価格設定に導きます。
- 利益配分の適正化
- グループ全体での最適な原価構造の構築
- 税務コンプライアンスの強化
コスト削減と業務効率化
「連結原価管理」により、グループ内の重複業務や非効率な工程を発見し、改善することが可能です。
- 調達の一元化によるスケールメリット
- 生産工程の統合による効率化
- 在庫管理の最適化
財務報告との整合性
連結財務諸表と管理会計の情報を連携させることで、経営層への報告精度が向上し、外部ステークホルダーへの説明責任も果たしやすくなります。
- 経営会議での迅速な意思決定
- 投資家・金融機関への透明性の高い説明
- KPIとの連動による経営管理の高度化
このように、「連結原価管理」は単なる原価の集計ではなく、経営の質を高めるための基盤となる仕組みです。次章では、導入にあたっての実務的な課題とその対応策について詳しく解説します。
「連結原価」の実務上の課題と対応策
これまでに述べてきたように「連結原価管理」は理論的には非常に有効な手法ですが、実際の導入や運用には多くの課題が伴います。ここでは、製造業における代表的な課題と、それに対する具体的な対応策を示します。
【課題①】 グループ横断の原価管理を統括するリーダーシップ部門の不在
グループ全体の原価管理を統括するリーダーシップ部門が存在しない場合、「連結原価管理」の推進自体が困難になります。
【対応策①】 グループ原価統括部門の設置やグループ横断会議による連携強化
対応策としては、グループ原価統括部門の設置に加え、本社経営陣から子会社トップへの説明と理解の促進が必要です。また、定期的なグループ横断会議の開催や、子会社側にも推進役を任命することで、グループ内の連携を高めることが必要です。
【課題②】 原価計算の方針・ルールの不統一
各子会社や部門が独自の原価管理を行っている場合、たとえシステム上で連結原価を算出できたとしても、業務的には意味をなさなくなります。
【対応策②】原価計算に関する方針やルールの設定と周知徹底
対応策としては、グループ全体で原価計算の統一的な方針やルールを定め(例えば、原価の配賦基準や原価要素の粒度や定義の統一)、これらのルールをグループ会社全体に展開・徹底することが求められます。
【課題③】 SCM系の業務プロセスの非統一
グループ各社でSCM関連の業務プロセス(購買、製造、在庫管理など)が異なる場合、原価データの整合性が取れず、比較・分析が困難になります。たとえば、購買・製造段階における不良発生時の対応や、製造時間の計測ルールが異なると、前提条件が異なるため、意味のある比較ができません。
【対応策③】 SCM系業務プロセスの標準化
対応策としては、原価計算ルールの統一に加え、SCM系業務プロセスの標準化(共通マニュアルや業務フローの整備など)を進める必要があります。
【課題④】 基幹系システムの不統一
グループ各社が異なる基幹系システムを使用している場合、データの粒度や定義が異なり、統合が困難になるケースがあります。
【対応策④】 基幹系システム利用ルールの見直しやシステム統一、新規導入の検討
対応策としては、まず原価計算の方針・ルールおよびSCM業務プロセスの統一を行い、それらが既存の基幹系システムで対応可能であれば、システムの利用ルールを変更することで「連結原価管理」に対応できます。一方、既存システムで対応できない場合は、基幹系システムの統一や新システムの導入も検討する必要があります。
これらの課題は、「連結原価管理」を単なるシステム導入ではなく、経営改革の一環として捉えることで、より効果的に進めることができます。
自社の現状の品目別実際原価の実現度について、1分程で簡易診断
「連結原価」の導入ステップと成功のポイント
「連結原価管理」の導入は、単なるシステム構築にとどまらず、企業グループ全体の経営管理の質を高めるための変革プロジェクトです。ここでは、「連結原価管理」の導入を成功させるためのステップと、実務上のポイントを具体的に解説します。
ステップ①:現状分析と課題の明確化
まずは、グループ各社の原価管理の現状を把握することが重要です。使用している会計・原価計算システム、業務プロセス、原価配分ルールなどを調査し、課題を洗い出します。
ポイント:
- 各社の原価管理レベルの差を可視化
- 現場ヒアリングによる実務課題の抽出
- 経営層と現場の認識ギャップの確認
ステップ②:原価計算ルールの統一
原価要素、配賦基準、分類方法などをグループ全体で統一し、共通の原価計算体系を検討します。また、必要に応じて、原価に関連するSCM系の業務プロセスの統一も検討します。
ポイント:
- 経理・製造・SCM部門の連携によるルール設計
- 実務に即した粒度と柔軟性の確保
- 文書化と社内教育による定着
ステップ③:導入するシステムの選定
各グループ会社からのデータ連携方法や採用する連結原価システムの選定を行います。あわせて、各グループ会社の基幹系システムについても、既存システムの継続活用か、新たに導入すべきかの判断も必要です。
ポイント:
- データ粒度・定義の統一
- 自動連携やパッケージの活用
- 導入ベンダーの選定
ステップ④:システムの導入
各グループ会社からのデータ連携の実装や、連結原価システムの導入を行います。実データを用い、想定通りの計算結果になるかの検証作業も重要です。
ポイント:
- 各グループ会社から収集するデータの精度
- 導入ベンダーのノウハウの活用
- 実データを用いた原価計算結果の検証
ステップ⑤:教育・定着化と運用体制の構築
連結原価管理の重要性を社内に浸透させ、継続的な活用を促進します。また、運用体制の整備も必要です。
ポイント:
- グループ原価統括部門の設置と子会社との連携体制の構築
- 社内研修・eラーニングの実施
- 連結原価情報を活用した意思決定の習慣化
「連結原価」のシステム実現手段
「連結原価」のシステムによる実現手段として、『①BOMによる連結方式』と、『②実績データに基づく連結方式』の2種類の方式があります。
『①BOMによる連結方式』は文字通り、各グループ会社のBOMを連結することで、連結原価を計算する方式です。
『②実績データに基づく連結方式』は、各グループ会社の購買実績や製造実績データを参照し、グループ会社を跨って非累加で実際原価の転がし計算を行っていく方式です。

『①BOMによる連結方式』は簡易的な計算方式であるのに対し、『②実績データに基づく連結方式』の計算方式は複雑ですが精度の高い連結原価が計算可能で、より高度な利用に適しています。
『①BOMによる連結方式』は、コストを抑えられる、期間を短縮できる面で優位性があり、『②実績データに基づく連結方式』は、以下の表に示す観点で優位性があります。

まとめ
本記事では、「連結原価管理」の概要やメリット、導入のポイントについて解説しました。
連結原価管理は、グループ全体の原価構造を可視化し、経営判断の質を高める有効な手法です。一方で、導入にはルール統一やシステム対応など多くの実務課題が伴います。特に、システム面では、既存の基幹システムの利用ルールやシステム自体の見直しが必要となる場合もあります。自社に最適な形で導入を進めるためにも、今回紹介したステップや対応策をぜひ参考にしてみてください。
《参考》弊社が提供する連結原価計算システム
基幹システムとして、現在SAP ERPをご利用中の企業も多いのではないでしょうか。
電通総研は、管理会計目的の品目別実際原価が可能な国内初のSAP専用の原価パッケージ:ADISIGHT-ACSをご提供しております。
ADISIGHT-ACSは、『②実績データに基づく連結方式』にて連結原価管理にhttps://erp.dentsusoken.com/solution/adisight-acs/も対応したソリューションです。
また、当サイトの以下のページに、製品概要や機能・特徴の説明、製品コンセプトを1分で解説したアニメーション動画を掲載しております。ご興味がございましたら、是非、ご覧ください。
連結原価管理で課題やお悩みをお持ちでしたら、ぜひ、電通総研までお声がけください!!