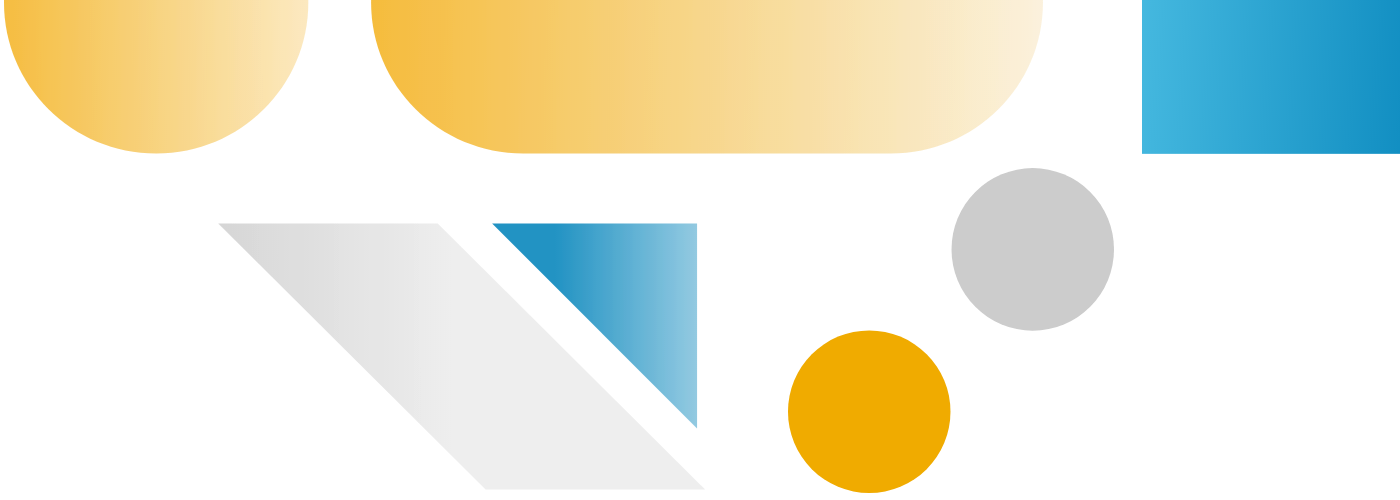SAP SDモジュールの主要なデータ構成や機能とは?(vol.120)
- 公開日:

SAP S/4HANAやSAP ECC6.0に代表されるSAP ERPは、業務プロセスを統合し、業績を向上させるために使用する包括的なERPシステムです。そのなかでも、SAP SD(Sales and Distribution)は、販売管理を担うモジュールであり、販売プロセスの業務可視化と標準化、また分析を実現するうえで重要な役割を果たします。
本ブログでは、SAP社製ERPシステムのSD(販売管理)モジュールについて、主なデータ構成(組織・マスタデータ)や機能、FI(財務会計)モジュールなどその他主要モジュールとの関わりに焦点当てて解説します。
*SAP社製のERPシステムは、業務領域ごとの機能群=「モジュール」で構成されます。
モジュールについて、詳しくは「SAP入門 ~モジュール・用語などをわかりやすく解説~(vol.101)」をご覧ください。
販売管理システムの目的とは
販売管理システムの目的を一言で表すと、販売プロセスの業務可視化と標準化をリアルタイムで行うことです。
販売の業務フローは、「引合い(ひきあい)→見積もり→受注→出荷→請求」という流れで進みます。それぞれのプロセスでは、引合伝票・見積伝票・受注伝票・出荷伝票・請求伝票などの伝票登録作業が発生します。
販売管理システムは、これらの伝票登録データを一元管理し、販売プロセスをリアルタイムで可視化/標準化することで、受注・出荷といった販売に関連する業務の効率化や正確性を向上させる重要なシステムです。
SAP SD(販売管理)モジュールのデータ構成
この章では、SAP社製ERPシステムのSD(販売管理)モジュールで使用する主な組織・マスタデータを紹介します。
組織・マスタデータは、販売管理モジュールを理解するうえで重要な構成です。
- SD(販売管理)モジュールの組織
SAPにおいて組織とは、企業の業務プロセスを階層的に反映させたまとまりのことです。
SD(販売管理)モジュールでは、会社コード、販売組織、流通チャネル、製品部門、営業所、プラント、出荷ポイント、保管場所があります。それぞれの組織のつながりは以下の図のようになります。

それぞれの組織は、上図に示したようにデータに関連を持っています。どのように関連しているのかをそれぞれの組織説明とともに解説していきます。
組織
- 会社コード
法人および独立会計単位です。この会社コードレベルで貸借対照表・損益計算表を作成します。
例えば、グループ会社もまとめて法定財務諸表を作成したい場合は1つの会社コードになり、それぞれで法定財務諸表を作成したい場合は、グループ会社の数だけ会社コードを作成することになります。 - 販売組織
販売に関するデータを全て管理する組織です。
必ず1つの会社コードに紐づけをする必要があります。販売組織の定義はプロジェクトによって様々ですが、地域別・国別・国際的な市場の区分別などでわけられることがあります。
データの一元管理するために販売組織を1つのみで運用するといった場合もあります。 - 流通チャネル
商品やサービスを得意先に届ける形態ごとにグルーピングした組織です。
例えば、店頭販売とインターネット販売などで流通チャネルをわけるといった運用をします。流通チャネルは1つの販売組織に紐づけられます。 - 製品部門
商品やサービスをグルーピングした組織です。
例えば、オートバイ最終組み立て・予備部品・修理サービスや見込み生産・受注生産のように関わる製品・サービスや製造工程ごとにわけるといった運用をします。製品部門は1つの流通チャネルに紐づけられます。
販売組織・流通チャネル・製品部門をまとめて販売エリアと呼称されます。1つの会社コードに対して複数の販売エリアが紐づけられます。
販売エリア
- 営業所
取引や販売で使用する組織構造を定義したものです。
例えば、東京本社、大阪支社、名古屋支社といったように地域ごとにわけるといった運用をします。営業所は販売エリアの組み合わせに対して紐づけられます。 - プラント
在庫管理・生産拠点・物流拠点・販売活動などをグルーピングした組織です。
プロジェクトによっては1つのプラントとして運用することもあります。
プラントは1つの会社コードに紐づけられます。 - 出荷プラント
出荷活動を管理する組織です。各出荷は1つの出荷ポイントのみで処理をされます。
出荷ポイントは1つのプラントに対して紐づけられます。 - 保管場所
製品を保管する場所をグルーピングした組織です。1つのプラントに対して紐づけられます。
SAPシステムにおけるマスタデータとは、データの基本的な構成要素であり、業務に必要な情報を一元管理可能です。販売管理モジュールで使用する主なマスタデータには、得意先マスタ・品目マスタがあります。
マスタデータ
- 得意先マスタ
BP(ビジネスパートナー)マスタデータの中で得意先としてロールを与えたもののことを言います。
1つのBPマスタで、仕入先としても得意先としても使用が可能です。これによりデータの一元管理が可能となっています。 - 品目マスタデータ
品目に関する詳細な情報(名称・質量・税関連など)が入っているデータです。
製品部門・出荷プラントなどの組織にもかかわるデータであり、SD(販売管理)モジュールだけでなくFI(財務会計)モジュール・CO(管理会計)モジュール・購買在庫管理(MM)モジュール・PP(生産計画管理)モジュールでも使用されます。
ここまで紹介してきたように、組織とマスタデータにはそれぞれ情報が入っています。そして、それらを組み合わせることで販売プロセス業務の可視化/標準化を実現しています。
SAP SD(販売管理)モジュールの機能
この章では、販売管理モジュールの機能について解説します。販売管理モジュールをどのように使うのか・何ができるようになるのかを順に説明していきます。
販売管理業務での主なフローは、引合い・見積・受注・出荷・請求です。それぞれのフローで業務の完了を証明する伝票の作成があります。販売管理モジュールでは、それぞれの伝票を登録することでデータの一元管理を可能にしています。ここでは、登録作業ごとに解説をしていきます。
1.引き合い
- 引合伝票の登録
販売業務で最初に行う業務は、引合いです。販売管理モジュール内では、引合い業務として引合伝票の登録をします。見込み客の管理、品目および数量などのデータを登録します。これにより商談の可能性を逃さず、効率的に管理可能です。 SAP SD(販売管理)モジュールでは、得意先コード・品目・数量などを入力して登録します。また、引合伝票を参照して、見積伝票や受注伝票の登録を行うことができます。
2.見積
- 見積伝票の登録
該当する得意先コード・品目コード・数量・納期を入力すると、入力した情報に基づき、あらかじめ設定された条件から価格が選択できます。これは、どの得意先から、どの品目で、どの納期期間でなどの情報から自動的に価格を算出してくれる機能です。 SAP販売管理モジュールを使用せずに、見積管理のみSAP以外のシステムで行うといった運用も可能です。
3.受注
- 受注伝票の登録
見積からお客様が発注すると、次に必要な業務は受注伝票の登録です。ここでは、販売管理モジュールの機能を使って、見積伝票を参照して受注伝票を作成できます。受注伝票登録をすると、出荷できる在庫数と所要量の過不足が自動的に計算されます。
このように受注登録を行う際に、在庫確認や得意先の与信管理まで先のプロセスを見越して登録ができる機能もあります。
4.出荷
- 出荷伝票の登録
受注伝票の登録完了後は、出荷伝票を登録します。
出荷伝票登録も受注伝票を参照して登録することができます。出荷の際には、ピッキングや出庫転記の業務が必要になります。ピッキングを行った際にはピッキング数量を入力、ピッキング完了後には出荷伝票を参照して出庫転記の登録することができます。
5.請求
- 請求伝票の登録
最後は請求伝票の登録です。出荷伝票の中で出庫転記まで完了したものを参照して請求伝票の登録を行うことができます。
このように、販売管理モジュールでは販売業務プロセスをそれぞれの伝票を紐づけることによって、一元管理することができます。また、販売に必要な在庫の数量や出荷状況など販売業務以外のデータもリアルタイムに参照をして管理することが可能です。
その他のSAPモジュールとの関わり
SAPには、SD(販売管理)モジュール以外に、FI (財務会計)・ CO (管理会計)・MM(購買在庫管理)・PP (生産計画管理)モジュールがあります。それぞれのモジュールのデータは、該当するモジュール内だけでなく他のすべてのモジュールに関わっています。
ここでは、SD(販売管理)モジュールが各モジュールにどのように関わっているのかを販売管理業務フローに従って解説します。
販売管理業務で、受注登録を行うとそのデータに従って生産計画(BOMや製造指図の作成)を行うことができます。登録された受注伝票データからPP(生産計画管理)モジュールよって、所要量展開(MRP)・製造指図の発行・製造指図に対する実績登録といった処理を行います。
次に、出荷伝票の登録の際に、在庫数と所要量の比較を行いました。この在庫数の管理は、MM (購買在庫管理)モジュールで行っています。
出庫転記をした際には出荷伝票とともに入出庫伝票・会計伝票(原価/製品)が自動生成されます。入出庫伝票はMM (購買在庫管理)モジュールへとデータが反映され、現在の在庫数が自動で管理されます。会計伝票FI(財務会計)モジュールにデータが反映され、財務会計モジュール内で会計業務を自動的に処理します。請求伝票を登録した際には会計伝票(売掛金/売上)が自動生成されます。生成された会計伝票による仕訳処理が、FI(財務会計)モジュールで行われます。仕訳処理をしたデータから FI(財務会計)モジュール内でG/L勘定が作製されます。
そして、CO(管理会計)モジュールと SD(販売管理)モジュール・FI(財務会計)モジュールが連携することによって収益性の分析を行うことができます。SD(販売管理)モジュールや財務会計モジュールによって得た収益の情報を原価情報と合わせて分析することで、確度の高いデータを収集することができます。
*購買管理(MM)、販売管理(SD)、生産管理(PP)を用いたデータ分析について詳しくは「SAP MM SD PP を用いたデータ分析とは?(vol.12)」をご覧ください。
まとめ
ここまで、販売管理システムの目的からSD(販売管理)モジュールの構成・機能、他のモジュールとの関わりについて解説をしました。今回の記事で解説をしたSD (販売管理)モジュールの構成や機能については、SAPの全体像を把握するうえで必要な知識です。SAPシステムの販売管理機能を活用し、引き合いから請求までのプロセスを可視化・標準化することで、業務状況や収益情報を適切に把握、経営判断の迅速化をはかることで、企業の持続的な成長をサポートします。
弊社は、SAPシステムと独自のソリューションを組み合わせることで、SAPシステムを最大限活用するとともに+αの付加価値をご提供しております。
SAPシステムの導入・移行や活用でお悩みの際は、是非、お気軽にお声掛けください。
*本記事は、2025年5月1日時点の情報を基に作成しています。
製品・サービスに関する詳しいお問い合わせは、電通総研のWebサイトからお問い合わせください。
https://erp.dentsusoken.com/inquiry/